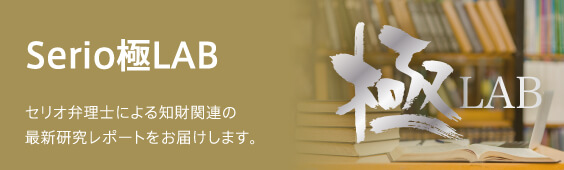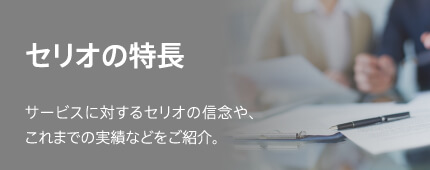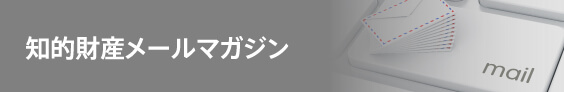<対象者> 企業経営者、事業責任者、知財法務部門、弁理士
Q:弊社甲は特許Aを保有していますが、乙社より「特許Aにつき通常実施権を許諾してほしい」との申し入れがありました。
通常実施権を許諾する場合、「競合他社には販売しない」など販売先の制限を付けたいのですが、独占禁止法との関係で問題はありますか?
A1:独占禁止法との関係
通常実施権を許諾する場合、もっとも注意する必要があるのは自社事業への悪影響、例えば、自社製品のシェア減です。
その対策として、ライセンス(実施)契約で自社事業への悪影響を最小限にすべく種々制限をかけることができますが、契約内容によっては不公正な取引とされ、特に販売先の制限は、不公正な取引として独占禁止法違反のリスクがあります。(参考:*1)
A2:その対策
上記のように、販売先の制限をかけることはできませんが、その対策として以下の方法により実質的かつ間接的に販売先の制限をかけることができると考えられます。
公正取引委員会ガイドラインの「3 技術の利用範囲を制限する行為」によれば、「当該技術を利用して事業活動を行うことができる分野(特定の商品の製造等)を制限することは、原則として不公正な取引方法に該当しない」とあります。(参考:*2)
特許請求範囲に異なるカテゴリーの請求項がある場合、請求項ごとに通常実施権を許諾できますので、以下のような対策が考えられます。
例えば、甲社は半導体封止材メーカーであり、特許Aの特許請求範囲が、請求項1(特定組成の半導体材料)、請求項2(請求項1を用いた半導体封止材)を含む場合、乙社へ請求項1の「半導体材料」のみ許諾し、請求項2の「半導体封止材」は許諾しない、とするライセンス契約が考えられます。
こうすることにより、半導体材料(請求項1)自体の権利は消尽しますが、それを用いた半導体封止材(請求項2)は許諾していませんので、競合の半導体封止材メーカーへは権利行使が可能で、実質的かつ間接的に半導体封止材メーカーへの販売を制限できると考えます。
A3:まとめ
よって、特許ライセンスを許諾することも想定して、特許出願時に異なるカテゴリーの請求項を作成しておくのが効果的です。
以上
(記:谷川 正芳)
参考:公正取引委員会ガイドラインから抜粋
*1 (2) 販売に係る制限
ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンス技術を用いた製品(プログラム著作物の複製物を含む。)の販売に関し、販売地域、販売数量、販売先、商標使用等を制限する行為(価格に係る制限については次項を参照)は、ライセンシーの事業活動の拘束に当たる。(一般指定第12項)。
*2 3 技術の利用範囲を制限する行為 (1) 権利の一部の許諾 ウ 技術の利用分野の制限
ライセンサーがライセンシーに対し、当該技術を利用して事業活動を行うことができる分野(特定の商品の製造等)を制限することは、原則として不公正な取引方法に該当しない。